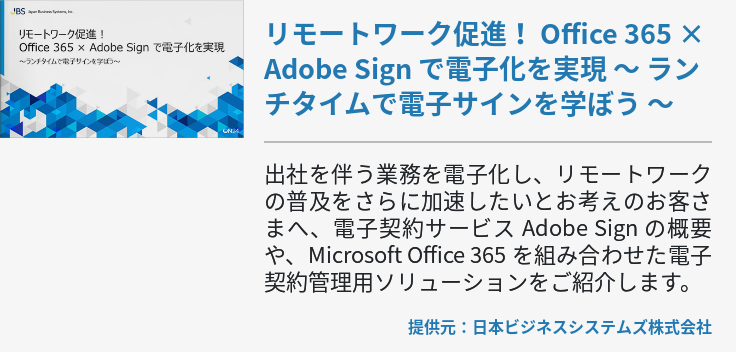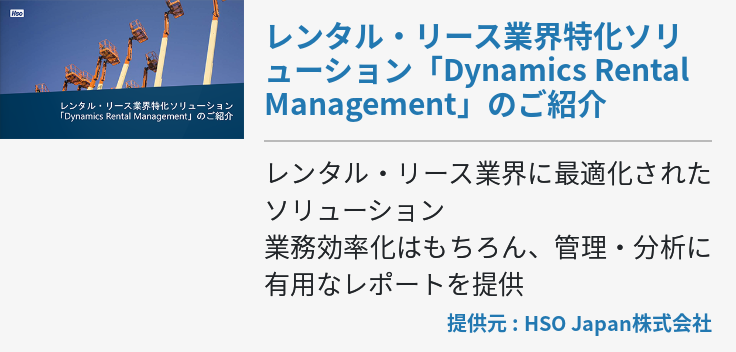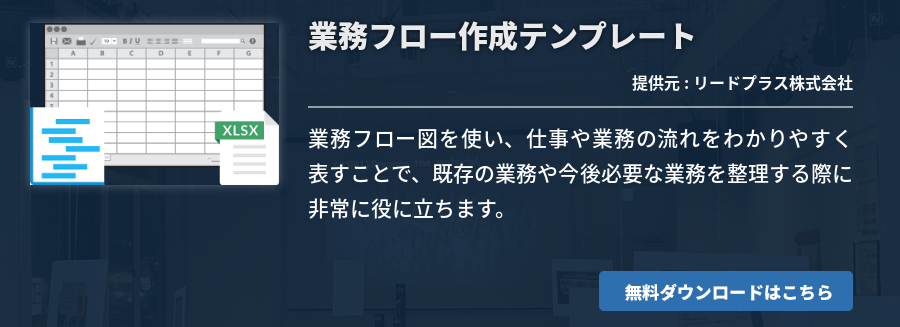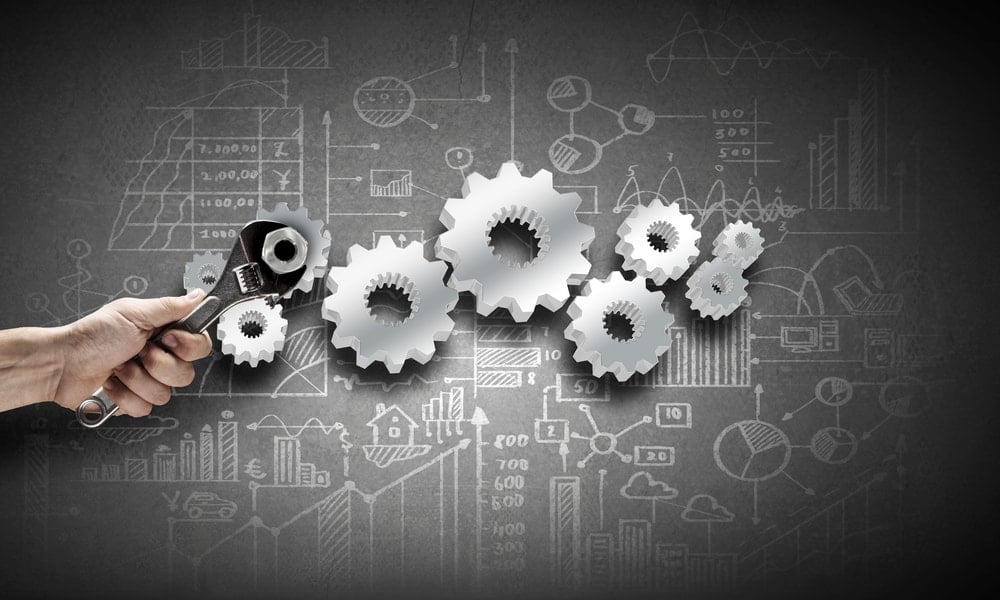限定的に人材を確保できることや、社会保険などの福利厚生費や賞与がかからないことから、派遣社員を雇用する企業が多いでしょう。繁忙期などのシーズンによって派遣社員を雇用することで、正社員のコア業務への集中化や人件費削減等の効果が得られます。
ただし、雇用形態の異なる人材が混在することで、人事面などで管理が複雑になるという問題もあります。加えて派遣社員の受け入れ時にチェックすべきポイントがいくつかあるため、漏れの無いチェックで派遣社員や派遣会社とのトラブルを避けなければいけません。
本稿では、派遣社員を雇用する企業が、人材管理を成功させるポイントについてご紹介します。
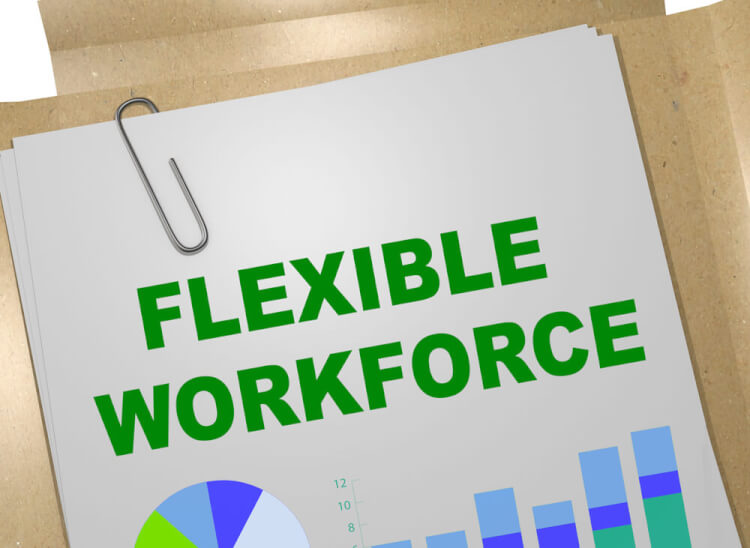
派遣社員について整理
人材派遣会社に登録されており、他の企業へと派遣される人材を派遣社員と呼びます。派遣社員は①一般派遣、②特定派遣、③紹介予定派遣の3つに分類されます。
①一般派遣
仕事を希望する人材を人材派遣会社に登録し、希望や条件に沿った派遣先企業との派遣契約が結ばれた際に、派遣社員として雇用契約を結ぶタイプです。「登録型派遣」とも呼ばれています。
②特定派遣
人材派遣会社と派遣社員が正社員同様の雇用契約を結び、必要に応じて派遣先企業にされるタイプです。派遣契約終了後も、派遣会社での業務が継続します。システムエンジニアなど特定のスキルを必要とする業種に多いでしょう。平成27年の派遣法改正により、一般派遣と特定派遣の法的区分が排除され、特定派遣でも厚生労働大臣の許可が必要になっています。
③紹介予定派遣
派遣社員が派遣先企業と直接契約を結ぶことを前提として、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うタイプです。とりわけ問題が無ければ、派遣社員は派遣先企業に正社員または契約社員として迎えられます。
派遣社員を受け入れる際のポイント
派遣社員の雇用というのは、単に人材派遣企業から希望に沿った人材を派遣してもらうのではなく、法的ルールが設けられているので受け入れ時のチェックが必要です。これを怠って後にトラブルに発展する例も少なくありませんので、以下にご紹介するポイントを必ずチェックしましょう。
1.期間制限
派遣先企業の同一事業所に対して、派遣社員を派遣できる期間は原則として3年間が限度です。派遣先企業が3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、派遣先企業の事業所における過半数労働組合などからの意見を得る必要があります。ただし、過半数労働組合の意見を聴取した場合でも、同じ派遣社員を同じ課で3年以上雇用することはできません。
以下の派遣社員や業務は例外として、期間制限の対象外になります。
- 人材派遣会社で無期限雇用されている派遣労働者(特定派遣)
- 60歳以上の派遣労働者
- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1ヵ月間に行われる日数が通常の労働者に比べて相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務
2.派遣契約の締結にあたって
派遣先企業は原則として派遣社員を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先企業が面接を実施すること、履歴書等を送付させることはできません。ただし、紹介予定派遣の場合は一定期間就業後に正社員や契約社員として受け入れる可能性があるため、例外として氏名や面接等が認められています。
派遣先企業が派遣契約の締結にあたり、注意すべきポイントを下記にご紹介します。
- 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務では派遣が禁止されている(紹介予定派遣は例外)
- 派遣契約を締結する前に、人材派遣会社に対して事業所単位の期間制限の抵触日の通知を行う必要がある
- 派遣契約では、業務内容などの他に、派遣先企業の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣社員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣社員の新たな就業機会の確保、派遣社員に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関することなど)についても定めることが必要である
以上のように派遣契約の締結にあたり派遣先企業が注意すべきポイントは非常に細かいので注意しましょう。
3.派遣就業にあたって
派遣社員の受け入れにあたり、離職後1年以内の人材の受け入れは法律で禁止されています。ただし、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されているため、退職後1年以内でも派遣社員としての受け入れが可能です。
さらに、これから受け入れる派遣社員に対して社会保険・労働保険の加入が適切に行われているかの確認が必要ですし、派遣社員からの苦情の処理体制を整備する必要もあります。派遣社員を管理するためには、受入事業所ごとに派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成する義務があります。
この他にも、派遣就業にあたってチェックすべきポイントがいくつかあります。
- 事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣社員がいれば、その派遣先企業の派遣社員に対しても正社員の募集情報を周知しなければならない
- 派遣先企業の同一組織単位の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある派遣社員について、人材派遣会社から雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するような依頼があった場合、その事業所で働く労働者を募集するときは、その派遣社員に対しても派遣先企業の労働者の募集情報を周知しなければならない
- 人材派遣会社に対し、派遣先企業の同種の業務に従事する労働者に関する賃金水準の情報提供などを行うこと
- 派遣先企業の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣社員にも実施すること
- 派遣社員に対し、派遣先企業の労働者が利用する福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を与えること
派遣先管理台帳の作成ポイント
派遣社員を含めた労働者が5人以下の場合は不要ですが、原則として派遣先企業の事業所ごとに派遣先管理台帳を作成する必要があります。主な記載項目は以下の通りです。
- 派遣社員の氏名
- 人材派遣会社の名称(事業主の氏名)
- 人材派遣会社の事業所名
- 人材派遣会社の事業所の所在地
- 無期雇用か有期雇用か
- 就業日
- 就業時間帯・休憩時間
- 業務内容
- 派遣先企業の事業所名
- 派遣先企業の事業所の所在地
- 派遣先企業の就業場所と部署
- 派遣社員からの苦情の処理について
- 教育訓練の実施日時、内容
- 派遣先責任者、派遣元責任者について
- 社会・労働保険の有無(無い場合はその理由)
- 紹介予定派遣について(紹介予定派遣の場合)
- 期間制限の対象外の業務の場合、その業務内容
作成した派遣先管理台帳は、派遣期間が終了してから3年間保存する義務があります。こうした管理台帳を作成し、長期間保存するためにはExcelファイルで対応するのではなく、システム化による効率アップがおすすめです。人事管理システムで派遣先管理台帳等を一元的に管理することで、情報整理が行いやすく、派遣終了後の情報保存も容易に行えます。さらに、保存期間が過ぎた情報のライフサイクルを管理することも可能なので、不要な情報が溜まっていきません。今後、派遣社員を受け入れるという場合は、本稿でご紹介した内容をもとに、多数の点に注意した派遣契約を進めていきましょう。