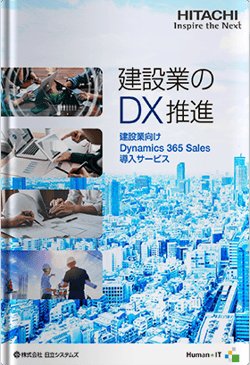どの国でもなくてはならない重要な仕事なのが「建設業」です。一口に建設業とはいっても非常に幅広い業種があるのをご存知でしょうか。ビルやマンション、一軒家を建てるのが建設業ではなく、建設に関わる多くの仕事も含めて建設業と呼ぶことになっています。
今回は、人々の生活と切っても切り離すことができない建設業について紹介するとともに、その定義や建設業に関わる29の業種について、それぞれ詳しく見てみましょう。

建設業とは?
まず、建設業とは、建設工事を行う仕事だけでなく、建設工事の工程で必要となるそのほかの仕事を含めたものを指します。工事を完成させることを「請け負う(請負契約)」ことが定義です。建設業法によって定められた建設工事の種類にある工事を行い、完成させるのが仕事です。
建設業の中には、一社で建築から土木工事などの過程をすべて元請けとして請け負って完成までを取りまとめる会社もあり、総合建設業としての意味合いを持つGeneral Constructor(ゼネラル・コンストラクター)、略して「ゼネコン」と呼ばれます。
建設業法上の分類として、29種類の業種があります。土木一式工事、屋根工事、電気工事などその種類はさまざまですが、どれも建設の工程に携わる工事であることがわかります。
29業種に分類される建設業
ここからは、29業種に分類される建設業について紹介します。建設業は「土木一式工事」と「建築一式工事」をはじめ、そのほか27種類の業種に分けられるのが特徴です。それぞれの仕事について、詳しく見てみましょう。
土木一式工事業
まずは「土木一式工事」です。総合建設業の1つで、土木工作物そのものを作る元請けのことを指します。建設物を作り上げるのはもちろん、その後の補修、改造や解体などあらゆる工事を含めて行うのが特徴です。実際の施工には専門工事の許可が別途必要になり、連携をとりながら建設工事を進めていく必要があります。
土木一式工事では、次のような工事があてはまります。
河川工事(改修などを含む)、道路工事(舗装や改良、開設)、トンネル工事、橋梁工事、海岸工事、ダム工事、空港建設工事、土地区画整理工事、大規模宅地造成工事、農業用水道工事、地滑り防止工事、森林土木工事などがあります。
空港や河川工事をはじめとする、人々の生活に欠かせない規模の大きな工事を請け負っており、各工程における専門工事を取りまとめながら工事を進めていく役割を持っています。もちろん、この各専門工事の取りまとめ(管理)は技術的なものではなく、工事の進み具合や調整などを行うもので、厳しいルールが定められているのが特徴です。
建築一式工事業
もう一つの総合建設業が「建築一式工事」です。建築確認が必要な建築物の新築・改修を行う元請けとして仕事を行います。そのルールとして、工務店がリフォームを行う場合など、1500万円以下であればこの許可は必要ありません。こちらも土木一式工事と同じように、実際の施工には電気工事や内装工事など、専門工事の許可が別途必要になります。
建築一式工事では「総合的な企画、指導、調整の基に建築物を建設する工事」という決まりがあり、専門工事業者を統括する場合には建築一式工事の許可が必要です。建築一式工事という名前から、どのような建築工事でもできるかのように思えますが、実際には建築を請け負うための許可であることに注意しましょう。
27の専門工事業
ここからは、すでに紹介した建築一式工事、土木一式工事のほかとなる、27の専門工事業について紹介します。実際の個別の工事は27の専門工事業に分類されています。これら27種類の工事は、それぞれについて許可が必要です。従来27業種でしたが、平成28年6月に「解体工事業」が加えられたことも、記憶に新しいでしょう。
では、それぞれの仕事について紹介します。
- 大工工事業
木材を使って建築したり、工作物に木製の設備を取り付けたりする建築工事業のことを指します。 - 左官工事業
建物の壁や塀、床など、こてという道具を使って塗る仕事を指します。 - とび、土工工事業
建築現場での足場組み立てから解体、重量物の運搬や配置、くい打ちをはじめ、コンクリートなどを使って基礎などの準備的工事を行う建設業を指します。 - 石工事業
石材を積んだり加工したりして工作物を作るほか、工作物に石材を取り付ける仕事を指します。 - 屋根工事業
瓦や金属、スレートなどを用いて屋根を作る(ふく)仕事を行う工事業です。 - 電気工事業
送電線から家庭への分電盤、照明器具など、電気関連の仕事を行う工事業です。修繕などの電気保安(保全)に関する仕事と、建築・建設現場で取り付けなどを行う2つの仕事があります。 - 管工事業
配管工事を行う工事業です。 - タイル・れんが・ブロック工事業
れんがやコンクリートブロックなどを用いて建築物や工作物を作るほか、工作物に対してタイルやコンクリートブロックを取り付ける仕事をする工事業です。 - 鋼構造物工事業
鋼板など、鋼材の加工や組み立てを行い鋼構造物や鋼工作物を作る工事業です。 - 鉄筋工事業
棒鋼などの鋼材を用いて加工、つなぎ合わせたり組み立てたりする工事業です。 - 舗装工事業
道路などの地盤を、コンクリートやアスファルト、砂、砂利などを用いて舗装する工事業です。 - 浚渫工事業
浚渫(しゅんせつ)は、河川や運河などの底にある土砂などを取り除く作業を行う工事業です。作業用の船を使って作業を行います。 - 板金工事業
金属の薄い板を加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製の付属物を取り付けたりする工事業です。 - ガラス工事業
工作物にガラスを加工し、取り付ける仕事を行う工事業です。 - 塗装工事業
塗料や塗材を用いて、工作物に塗ったり吹き付けたりする工事業です。 - 防水工事業
アスファルトやモルタル、シーリング材などを用いて水漏れしないよう防水を行う工事業です。 - 内装仕上げ工事業
木材や吸音板、壁紙の取り付けやたたみの取り付けなど、建築物の内装仕上げ全般を行う工事業です。 - 機械器具設置工事業
機械器具の組み立てをして工作物を建築したり、工作物に機械器具を取り付けたりするための工事を指します。立体駐車場設備工事やトンネルなどの給排気機器設備工事などがあてはまります。 - 熱絶縁工事業
工作物、または工作物にかかる設備を熱絶縁するための工事を行う工事業です。冷暖房設備や動力設備、燃料工業・科学工業等の設備の熱絶縁工事などがあてはまります。 - 電気通信工事業
無線・有線問わず通信設備の工事をはじめ、アンテナ工事、データ通信に関する設備工事を行う仕事です。 - 造園工事業
樹木の植栽や公園や緑地の築造を行う工事業で、500万円以上の造園工事を請け負う企業を営業するためには、国土交通省または都道府県知事に届け出をして、許可を得る必要があります。 - さく井(さくせい)工事業
専用の機械を用いて、温泉掘削や井戸、天然ガスや石油を掘るなど、掘削工事を行う工事業です。 - 建具工事業
工作物に木製または金属製の建具を取り付けるための工事です。内装仕上げ工事のあとに行われる仕上げ工事の一つです。 - 水道施設工事業
取水施設や浄水施設工事を行う工事業で、土木一式工事や管工事とは異なります。公道における下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事。家屋やその他敷地での配管工事や、上水道などの配水小管設置は管工事、そのほか、上水道の取水・浄水・配水などの施設築造や設置が水道施設工事業です。 - 消防施設工事業
消防用設備として、火災警報や消火設備をはじめ、避難設備などを設置、取り付ける工事業です。 - 清掃施設工事業
ごみ処理施設やし尿処理施設など、清掃施設工事を設置するための工事業です。 - 解体工事業
建築物や工作物の解体をして、更地に戻す工事を行う仕事です。以前はとび・土木工事業許可でできていた仕事ですが、令和元年5月31日以降は解体工事業許可が必要です。
建設業が共通に抱える課題とは
続いては、幅広い業種であることがわかった建設業が、共通で抱えている課題について解説します。どの建設業も専門的な知識や資格を必要としており、有能な人材が多い一方で、解決しなくてはならない課題も山積しています。複雑で属人的な情報管理
まず挙げられるのが、複雑で属人的な情報管理であるということです。建設業界には、法律や規制上、管理しておく必要のある対象が数多くあります。そのため、これらの管理対象については建設業者間でうまく連携を取っていく必要があると考えられています。
しかし、実際には情報の取り扱いが広く行われているわけではなく、うまく共有なされていません。情報の取り扱いが属人的な状態にとどまっていることから、非合理的であり、かつ経営判断がしにくいというデメリットがあります。
この課題を解決するためには、社内はもちろん社外との情報共有もスムーズに進める必要があります。情報共有しやすくなるシステムの導入を検討し、管理対象をリスト化するなど、情報管理を簡易化するのがおすすめです。
働き手の慢性的な不足
建設業界は、どの業種においても慢性的な人手不足が浮き彫りになっています。少子高齢化が進んでいることで働き手の数が相対的に減っていることをはじめ、資格取得などハードルの高い仕事が多く、人手が足りていない状態です。
また、建設業の多くは体力を必要とする仕事のため、現場で働く人の年齢層も高くなり、労働生産性の低下も問題になっています。
現場だけでなく、営業や事務などの合理化も必要で、今後も業界内で生き延びていくためには、あらゆる部分でのコストカットも望まれています。現場の労働力にも最適化が求められており、今後のためにも今一度現制度を見直す必要があるでしょう。
また、業務を簡素化できる部分などは業務管理システムを導入したり、情報共有のためのツールを導入したりするなど、新たな試みも必要です。
まとめ
建設業が抱える課題を解決するソリューションの一つとして、「Dynamics 365」と「Dynamics 365 for Sales」というツールをご提案します。これらは、社内での情報共有を円滑にするための機能が備わっており、現場で働く社員はもちろん、営業や事務などさまざまな部署にまたがって情報共有ができるようになっています。
物件や案件などの管理対象をまとめたり、他部署での情報共有をしたりするなど、組織が一丸となって情報のやり取りをするのに活用できるのがポイントです。